
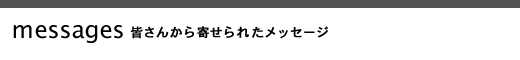
| 無題 2005年7月27日 誰も知らない 子ども達の演技がすごかった。柳楽君の一場面一場面の演技にとても驚いた。目がすごくて、本当に演技?と本気で思った。柳楽君がどんな人なのかすごく気になった。最後、子ども達がどうなったのかがとても気になる。  信じる心 2005年7月27日 ミルク それはとても大切で、最初に覚える気持ち その気持ちがあるかぎりどんな困難も乗り越えられる この映画を見てそんなことを思ってしまいました。 忘れていたことを思い出させてくれて 本当にありがとう。そして子供達が幸せになることを 心から祈っています。  今日もここに・・・・・・ 2005年7月25日 Grin ********************************************* *とても面白かったです。 ** *柳楽くんも良かったけどしげるが一番 **** *よかったです。 ** *********************************************  愛しい・・・ 2005年7月24日 風 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★ DVDでこの映画をみた ★ ★ 今まで、人生でみてきた映画の中で ★ ★ 一番悲しい映画だった。 ★ ★ でも、今までみてきた映画のなかで ★ ★ 一番私の心に触れた、なんか・・・・・ ★ ★ 言葉で表すのは難しいけど、 ★ ★ 人間がつくった、人間にしかつくれない ★ ★ 愛しい映画だった・・・・ ★ ★ 見おわった後、涙が止まらなかった。 ★ ★ 柳楽くんありがとう。 ★ ★ なんか、久しぶりに「愛しい」って ★ ★ キモチがあふれてきたよ。 ★ ★自分の兄弟とか親・・みんな愛しく思えた。★ ★ そう、みんな愛しく思えた。 ★ ★みんながそう想うことができたなら、、、 ★ ★ みんなまるく、円になれる ★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  生きる 2005年7月24日 SHIHO 今、毎日いろいろある中で、生きるってことがなんだか分かった気がする。 この映画をつくってくれた監督、スタッフ、YOUさん、柳楽優弥君、みんなに感謝です。 ありがとう。  全ての大人の子供時代へのオマージュたる傑作 2005年7月24日 鬼子母神 大人は子供に誰も知らない時間がある事を知らない・・・ 世間は子供たちが存在している事を誰も知らないで良いと思っている。 明と京子はアダルトチルドレンになる子供たちの、茂とゆきは無垢なる存在故に猛暑の駐車場や留守番中事故で死んでしまう無責任な親の犠牲者の、紗希は悪質な虐めにあう子供たちの、それぞれ現代の病巣とも言えるものの権化であろう。 私はこの映画を観て、ふわふわとして全く時間が止まっているかのような、誰も知らない夢の中みたいな自分の子供だった時間をヒシヒシと思い出した。  こどもたちをよろしく 2005年7月21日 subaltern 子供たちをよろしく・・・という映画を、ずいぶん前に見たのだけれど。外国の、ストリートチルドレンの話。愛された事がないから、愛し方もわからない、実話?なのか、救われないはなしだった。邦題しかわからないけれど、「子供たちをよろしく」と言う、そのタイトルが、ずっとわすれられない。最近まで、「神様、どうか、子供たちをよろしく・・」と言う思いが、込められているのだろうくらいに思っていた。自殺してしまう子もいたし。でも、是枝監督の作品をみて、今更だけれど子供たちをよろしく・・と、お願いされたのは私自身。映画を観て、知ってしまった、すべてのひとが、その映画の作り手にお願いされていたんだって、思いました。遅いかな。遅くても、それで、何か、できると、いいのだけれど。何が、できるだろう・・・?  幸せの責任 2005年7月20日 masa 誰も知らない。 たくさんの思い出がこみあげてきました。 両親が離婚したのは私が中学1年の時です。 父親の暴力と金遣い荒さが原因で離婚し、長男の私を含め3人の子供は母に引き取られました。父は家の金目のもの全てを持って行き、残った家のローンと私たち3人の子供が母に重くのしかかりました。母は住宅ローンと生活費を稼ぐため、昼は保険の外交員・ガードマン・シロアリ駆除を掛け持ち、夜はスナックで働き、睡眠時間2〜3時間しかない日々が続きました。毎日夜遅く酒のにおいをプンプンさせて帰ってきては、ゲーゲー吐きながら床につく母。その上金回りも悪く、いつも遅れて学校の給食費や学費を払いに行きました。離婚する前から、両親は自営で夜の商売をしていたので家を空けることが多く、兄弟3人で家事をこなし夜には留守を守ることが日常で、映画のワンシーンそのままの生活にも耐えがたいものがありました。周りの友達は両親が居て、何不自由ない生活。私の家族の生活は誰にも言えないものでした。その時の閉鎖的な描写がこの映画にも表れていて、あのときの記憶が鮮明によみがえりました。 今回映画を拝見させて頂いて改めて、私たち子供を育てあげてくれた母を誇りに思います。 当時、母はどんなに苦しかったんだろう。どんなに辛かったんだろう。どんなに孤独だっただろう。 捨てられない子供を守る重圧に耐えた母をみて育った私は今、かけがえのない家族がいます。私はこの家族を諦めたりすることはありません。それが育ててくれた母への恩返しだと思っています。 普段忘れてしまうような身近な出来事をクローズアップしたような心情に訴えかける作品を期待しています。 失礼致します。  胸がチクチク 2005年7月17日 藤原ゆか 子供の視線が自分にチクチクと刺さる感じだった。 子供たち一人一人をハグしたい気持ちになる。 自分もまだまだ子供だと感じていたが、 映画の中のような純粋に人と信じたり、 生きようとする気持ちは無いような気がした。 自分が子供の皮をかぶった大人(劇中の)のような 気がしてチクチクした。 悲しさを感じたけど、ただ好きだと思える映画だった。  危険 2005年7月11日 吉田 遅ればせながら誰も知らないを拝見させていただきました。子供達の姿、YOUさんの演技はすばらしかったです。彼らの存在感は、この映画に対する賞賛の大きな要因になっていることは間違いないでしょう。 しかし、私はこの映画を見た後、怒りにも近い苛立ちと危機感を抱きました。子供達を捨てた母親に対する怒りではありません。この題材をこういう形で描いた監督に対する怒り、そして、それに対する世の中の賞賛に対する危機感です。 ドキュメンタリータッチで描いていながら、子供達の言動や心の変化はきわめてリアリティーに欠き、ファンタジーとなっています。 たとえば、初めてできた外の世界の友達に万引きを命じられるシーン。明の境遇に置かれた少年は、躊躇はしても最後は万引きをするでしょう。そしてその行為こそが、少年の心の隙間、初めての友達にすがりつきたい悲鳴を表現するのではないでしょうか。 子供の心は子供のルールで変化するものであり、大人の心の方程式は当てはまらないと思います。それゆえに、ゆがんだ時は大人の想像を超える残酷さや大胆さとなって表面化するときがある。そうしたリアリティーがなかったように思います。明の言動が大人の方程式で理路整然と描かれていたように感じます。 また、リアリティーのなさにつながった決定的要因は、子供達がみな、健全に自分自身を大切にし続けていること。親に捨てられた子供はその程度の差はあれ、必ず自分自身に価値を見出さなくなるはずです。そしてそれが子供を自傷行為や他者への暴力、脱法行為に向かわせる。残酷な描写を含まなくても、自分を無価値と感じている子供達を表現することは可能だったのではないでしょうか。監督は「置き去り事件のようなことが再発しないためにも映画を見てほしい」という趣旨のことをどこかでおっしゃっていましたが、もし本当にそう思っているのであれば、この映画はまったくその意図に逆行すると思います。本当にそう思ってこの映画を作ったのであれば、監督ご自身が巣鴨の事件の本質を理解されていないのではないかと危惧します。子供達の幼少時の経験は、人格障害などの形で一生涯にわたってその後の人生を汚染します。その重みを本当に理解していたらこの映画は作れないのではないかと思います。同様にこの映画を賞賛する人達はその重みについて誤解し、危機感を欠いたまま分かったつもりになってしまうのではないか、と危惧します。 これはフィクションです。しかし、実際の事件をモチーフにしていることを前面に出している以上、見るほうはその事件と結び付けて見ます。そしてフィクションだといわれても、ドキュメンタリー風の演出もあいまって、観客はこの映画をリアリティーとして見ます。その影響について、監督はどのように責任を負われるのでしょうか。 蛇足ですが、人々に問題意識をもってこの映画について考えてほしいと思っていらっしゃるのであれば、HP上に賞賛のメッセージのみではなく、批判意見も載せてみてはいかがでしょうか。もし監督に今もドキュメンタリーの精神が生きているのなら。  無題 2005年7月10日 smile この映画を何度見た事でしょうか なぜか私の生活の中の一部になっています 一度目は息ができないくらい胸がつまり 二度目は涙が止まらず 三度目は子供の前なので気丈(つもり)に はじめは一人二度目も そして三度目は子供たちと監督がこられると新聞で見て 何度も映画館に子供を連れて行ってもいいかと問い合わせをしながら監督に会いに行きました 子供(4歳と8歳)に見せていいのか 監督の話の邪魔にならないか ずいぶん迷いましたが どうしてもどうしてもこの映画をつくられた 監督に会いたかった うちは母子家庭です 子供を置いていくわけにもいかず 一緒に連れて行きました 子供に見せるの? みたいな周りの視線や言葉 ある方の質問のときにこの映画の母親はだらしな い女性だという言葉 それに対し母親を責めてるわけじゃないといった監督の言葉 私はその言葉を聴いた瞬間 子供の前で涙をとめることができなくなった その言葉が聞きたくていったような気がする 私を許してくれる人がいると 嬉しいとも違うでも何か胸のつかえが少し軽くなったような言葉にはできない感情があった 離婚して子供や親に負い目もある 周りの言葉に傷つき かわいそうと思われたり 自分では何ともないつもりでいても 責められているような気がすることがある 私は子育てをしているが気持ちの上で 子供から逃げ出してしまうこともある この映画に出てくる母親と自分を重ねる 親の勝手な都合で子供を振り回していることには違いないけどがんばってる 誰の責任にもせず自分の責任にして 私も一生懸命がんばってることを 認めて許してもらえたい この映画はあなただけが悪いんじゃないよって言ってくれる DVD発売後は何度も子供とせりふを覚えるぐらい見ている 見た後はいろんな話をする事もある そして今見ると私も子供もがんばろという気持ちになれる 今は見終わった後笑顔になれる これからも何度も何度も見ると思います その時その時の自分に重ねながら 子供も歳を重ねるごとに違う見方をし 感情を変えながら 私たちにとってとても大切な映画です 先日 柳楽くんの新しい映画のキャンペーンに行きました 失礼なのかもしれないのですが 明に会いに行きました 明が笑っていて嬉しかったです  ずっと心に残しておきます 2005年7月7日 ちく 映画を観ているという感覚ではなく、すぐそこに こんな子供達がいる事を見ているような感覚を覚えました。一般論とか、人の目を気にして生きるとか。現代の社会の中で、このような現実があるということに、誰も気が付かない。 それなのに、なぜ人の目を気にするのだろう。 自分の敵は自分なんだということに、気付かせてくれた作品です。 自分らしく、自分を信じていきること。 愛の尊さと生きる勇気を見つめさせてくれて、ありがとう。  異常の中のぬくもり 2005年7月4日 ワタナベ 世間から見たら異常にも取れる4人の生活に、家族のぬくもりのようなものを感じました。また、そこには母親を信じてひたむきに生きる彼らの日常があった。この作品の演出には同情や憐れみを寄せ付けない尊いものを感じました。  だから・・・ 2005年6月25日 Mai 子供の頃、親に捨てられた事がある。 駅のホーム。喫茶店。小さなアパート。3回。 僅かな希望を打ち砕いて、母は戻ってこなかった。 だから、私は自分の子供を1分だって待たせない。 喫茶店でトイレに行った母親を、首をのばしてキョロキョロ待つ子供を見ると、切なくて泣けてくる。 アパートの部屋で、ひっそりと子供だけで数ヶ月暮らした事がある。 暗い部屋で、白いご飯にお醤油をかけて食べていた。お米が無くなったら、空腹を紛らわす為に氷を食べていた。 だから、自分の子供にはいつも満腹でいてほしい。 だから、我が子が玄関の呼び鈴の音にビクビクしない事が嬉しい。 大人になった兄の家の冷蔵庫は、いつも食料で満杯だ。「食べ物が入ってないと不安になる」だから・・・。 学校に通わなかった空白がある。 記憶が抜け落ちている。 だから、子供が朝学校へ行くと、ただそれだけで涙が出そうになる。 母親は絶対だ。 良い暮らしをさせてくれる親戚の家に預けられるより、貧乏でも母親と一緒が良い。 この映画を見て、驚いている人もいるかもしれない。 でも、今もどこかに、この子達はいるのだ。 今日、自分の子供と公園で遊んでいた子も、遊びに来ておやつを食べていった子も、どの子がそうだったとしても、不思議はない。 外に出れば、明るく挨拶もする。時間が来れば帰って行く。 でも、帰った場所はあのアパートかもしれない。 母親に恥はかかせられない。 もし戻ってきたときに困るから。 女が一人で子供を育てる大変さ、生活にどれだけお金が必要で、どれだけ頑張ればどれだけ稼げるか・・・「誰も知らない」 感動なんてしない。 一生懸命、守ろうとしていたものが同じだったから、 だから・・・現在の彼らは今の私のように、普通の暮らしをしていると、思いたい。 私も、そのときは一度も泣いたりしなかった。 誰に同情されても、心配だったのは、 戻ってきた母親を誰かが怒ること。 何もかもがリアルで、 家の家族はこの映画を話題にしない。  心にずっと残っています・・・ 2005年6月23日 かほ 去年の秋にこの映画を劇場で観ました。とても感銘を受けました。目で語る演技。母親と兄弟への愛情。決して子供を愛さなかったわけではない母親。まだ大人でもなく・・・幼い子供でもない私には日本の社会にしか疑問を持つことができませんでした。 この映画を観終えた時、大人になっていつか子供ができた時、物質的なものではなく精神的な心の糧になるようなものを与えられる大人になりたいと思いました。  涙 2005年6月21日 goto 劇中涙を流すのは母親だけで、子供達は一度も涙を流さない事に気づきました。子供達にだって涙を流したくなるような時があったはず、しかし彼らは一度も一滴も涙を流さない、それが彼らの強さなのだろうか。 私はこの映画を見て涙はでませんでした、というか出せませんでした。 もしも涙を流してしまったらきっと私は彼らの事を理解するに値しない存在になってしまうだろうと思ったから。 この涙を流さないという演出感激です!素晴らしすぎる、そして決定的です! できれば監督さんに詳しくこの演出について教えていただきたいです。  衝撃的な現実 2005年6月20日 古賀 信之 カンヌ映画祭主演男優賞を受けた是枝監督の映画『誰も知らない』を観た。実際に起きた事件をヒントに作られた映画であるという。何よりも衝撃的なのは、育児を放棄した母親の家出で、4人の兄弟姉妹が1DKの小さな賃貸アパートで、電気も水道も止められたままで数ヶ月間生活をしたという事実である。経済大国の現代日本で、このような事件が起きたということである。フリーター的職業についている母親は、4人の子供を学校に行かせずに、「自分のやりたいこと」を希求しながら生きている。現在約400万人の、「自分のやりたい」仕事を求めて不安定な労働条件下に働いているフリーターの若者達が、もし子供を持ったとしたら、この映画のような状況になるだろう。日本政府は、憲法25、26条で定めている健康で文化的な最低限度の生活と教育を受ける権利を保障する福祉行政を行っているのだろうか。映画の中で、「学校に早く戻りたい」と母親に訴える長男の明は、「生活保護を受けると、兄弟姉妹4人の共同生活が出来なくなる」と、その非人間的な対応に反撥して言う。福祉行政は、マニュアル通りでなく、もっと人間的な対応をする必要があるのではないだろうか。  洋服タンスの中は母のぬくもり 2005年6月20日 あたしもkyokoという名 カップラーメンの空き容器に育った植物たち。 ふき取った後の床のしみ。 ・・・・・押入れのキョウコ。 ・・・昔のあたしを診ているようで 診ていられなかった。 当時のあたしは、出勤時に母親が与えていく 500円札で食事代にあてていた。 かにぱん(現在も売られていますね)を買ってきて、かにの足の部分を一本ずつちぎってかみしみて食べていましたね・・・・・ 映画を観ながら・・・ 過去の自分を診ながら・・・ スクリーンの中の描かれた日常 と 生きてきた幼年時代の脳裏が いったりきたりして、 こんなに密着できた感触の映画は初めてです。 帰宅して、 泣きました。 涙が止まらなかったので、 家族に気づかれないようにするのが たいへんだった・・・  感動しました。 2005年6月19日 さくら はじめまして。私は今日始めてこの「誰も知らない」を見ました。とてもきれいな映画でした。親は帰ってこない、そう頭ではわかっていてもどこかで母親がこの少年たちの中にはいるんでしょう。そして今私の中にもきっと親という大きな存在があるのではないでしょうか。とてもきれいでした。小さなころに戻ったようです。終わりのない「お留守番」を疑わずにまっているこの少年たち。なぜここまで大人の力を借りないのでしょう。なぜここまで一途に生きれるのでしょう。見終わったあとに確かなものがなにか私の残りました。とてもきれいな映画でした。ありがとうございます。  わたしを変えた映画 2005年6月17日 ふくだひろし わたしは映画はあまり見ないのですが、「誰も知らない」を観て何十年かぶりの感動をどうすこともできずにメールを差し上げることにしました。 少年が親に捨てられた兄弟姉妹の面倒を見るという設定そのものに感涙をさそうものがあるのでしょうが、しかしその姿に大人である自分が救われ癒されていることに驚きを覚えています。正直いって、この映画はわたしの人生をある意味で変えてしまったように思います。たとえば「長屋紳士録」を観たときの感動に少し似ているかもしれないし、「銀河鉄道の夜」を読んだときの深い癒しにも通じるような気がします。 明君は現代へ使わされたアヴァロキテシュバラです。「あきらむ」という言葉は心を明るくたのしくさせるという意味と、ものごとをくもりのない眼で見極めるという意味があるそうです。大人たちのエゴや欲望や勝手に振りまわされても、とがめたてたり不平をこぼしたりせず、ただやさしい心で必死に幼子たちを守ろうとする明君は現代のアヴァロキテシュバラです。この映画の企画を支えたものは「怒り」だったが、柳楽優弥君の存在を得たことでそれが愛情に変わったと監督は述べられています。この映画は、醜いエゴを責め立てることによってではなくて、そうしたもをくもりのない眼に映し出すことによってカタルシスと覚醒をもたらしているのではないでしょうか。だからこの映画は深刻な状況を描いていながら、童話のもつ癒しと赦しをもって観る者の心を打つのだと思います。  無題 2005年6月15日 ng 自分がはじめて心を打たれた作品です ご活躍をお祈りします  是枝監督作品を初めて劇場で観ます。 2005年6月13日 裕美子 オーストラリアのブリスベン在住の者です。是枝監督の作品は、テレビでたまたま観た「記憶が失われた時」以来、どれも興味深く拝見させていただいています。特に、「幻の光」は大好きな映画です。外国で生活しているため、監督の作品を劇場で観たこ とは、残念ながらこれまで1度もありません。先日、「誰も知らない」が7月の初旬からブリスベンでも劇場公開されると聞き、大変嬉しく思っています。  無題 2005年6月11日 ai すごくいい映画でした。 明たちは、しっかりと、‘今’を見つめて生きていて、心のどこかで母が帰ってくるのをまっている…。 ずっと途絶えていた母からの仕送りが来たシーンがあったと思うのですが、そのときの明の心を考えると、なんというか(言葉でちゃんと表せれないのですが)、最悪の時に、ひとすじ光がみえたような。母に忘れられてなかったんだという安堵感(母への怒りとは裏腹に)と、取り返しがつかなくなってしまったかもしれない事への不安が渦巻いていたんだろうと思うととても心苦しくなりました。 中学生の少女に助けを求めたのはもう本当にぎりぎりの所だったからなのかと思います。それでも落ち込むこともなく、今、これから、何をしていけばいいかを考えて懸命に生きている。本当のこころの強さっていうのはこういう事なんだと思い知らされました。  無題 2005年6月11日 raica ごはんを口いっぱいに詰め込んで、泣くのを我慢してるときの切ない気持ちになりました  無題 2005年6月8日 fbkh 後からジワジワと考えさせられる映画でした。 この子どもたちの現状を目の当たりにすると、何かしてあげたいと切に思うのですが、 実際もし近くにいたら、力になってあげることができただろうか? 近隣に関心を抱かないことが、当たり前の都会のアパートの中で、私は気付くことができるだろうか。 薄汚れていく服装、生ゴミのにおい・・・、目をそらしてしまうかもしれない・・・。 子どもたちは助けを求めているが、それは、福祉じゃなく、先生じゃなく、近所のおばさんじゃなく、ただ母親だけなんだ、ということが、切なくて切なくて、・・・。 子どもの真っ直ぐさ、たくましさ、かよわさを胸にドンと突きつけられました。  いい映画でした。 2005年6月7日 demimama 感動しました。ありがとうございました。 子供が2人いますが、時々、子供の声のしないところに行きたくなる事があります。たとえば私が入院するとか…。一週間蒸発するとか…。今のところ願望だけですが、それだけ自分の日常に疲れていました。それが映画を観てから心が優しくなり、子供の声にも耳を澄ますようになりました。日常が今までと違って感じられるようになりました。 是枝監督とは同い年です。1988年当時は、海外で仕事をしていてこの事件について何も知識がありませんでした。監督の88年からの想いを”誰も知らない”という形になさった事に尊敬の念を感じます。 柳楽君は世界が唸った理由がわかります。夏の場面で、それまでとの変化に驚きました。イライラを妹弟にぶつけているシーンは真に迫っていました。どんな風に演出なさったのですか? 京子ちゃんは、ボッティチェリのプリマベーラを思わせました。ゆきちゃんは、ETで登場したドリューバリモアを思わせました。紗希ちゃんは、山口百恵が引退してから私にとっては、初めてのポスト百恵でした。しげるくんは、最高にいい味をだしていたと思います。天性の何かを持っている感じがします。YOUさん素敵でした。ベストキャスティングだと思います。 子供が生まれて出生届けを出すという行為を、とても厄介に思う人もいるだろうなと想像します。海外へ行ってはみたいと思うけどパスポート作らなければいけないとなると思考停止してしまったり…。とにかく手続きというもの、提出物というものが妙に苦手な人。仕事は人並み以上にできる。恋愛力もある。母親になったとしたら子供に愛される。だけど出生届けに限らずただ手続というものが苦手。…なんかそんなところから悲劇が始まっているような気がするし、この悲劇は今でも存在しているのではないでしょうか。明たちの学校に行きたいという気持ちが伝わってきて、この日本でこんな子がいるなんてと胸が痛みました。 長く書きすぎました。お許しください。  ココロが痛みます 2005年6月7日 じゅんこ ず〜〜っと観たかった作品で、でも田舎に住んでるので劇場でも見れず、やっとレンタル開始されて観ました。予備知識が入っていたせいもあって、かなり観るのが大変でした。切な過ぎて。 もう、そのココロの痛みが、ずっと取れてくれなくて、どうしようもなくて、朝からずっと、ぼんやりしています。 子供に恵まれず、3年が経ちました。 不妊治療中ですが、子供は生むまでがゴールではないことを改めて思い知らされました。  無題 2005年6月7日 凌 最後の結末が悲しかった。 明の淡々とした口調や表情が私を戸惑わせた。 悲しいと泣くこともせず ただ いまを受け入れ 生きていく そのまっすぐな姿にわたしは怯んでしまった。 私だったら 泣きわめいて 暴れまくるだろう。 そんな私は 「子ども」なんだろうか。 「大人」なんだろうか。 大人になると 精神は屈折して 心が弱くなるのかもしれない。 子どもたちのほうが ずっと 腹が座って 邪気がなくまっすぐだ。 たのしいときも つらいときも。  子供 2005年6月6日 k あんなにも狭い世界の中で生きる子供。 その狭い世界の中でさえ、あんなにもたくさんの人がいる。 本当に誰も知らないのでしょうか? 知っていたら何かできるのでしょうか? 純粋な明たちを見ていて胸が痛みました。 私が流した涙は何か形にしたいです。  再び 2005年6月6日 alf's mom 9年前乳癌の手術と治療の為2ヶ月ほど入院した事があった。入院の日、「このまま家に帰ることはないかも」と思って家を出た。小2、小5、中2、中3の子ども達に病名は言わなかった。幸いにして手術は成功、治療もうまく行った。でも心のどこかに「帰れるかな」 の思いはあった。でも子ども達は違った。日曜ごとに病室を訪れる子ども達の表情はいつも笑顔だった。子ども達にとっては「今生きている母親がそこにいる」それで十分だったのだ。子ども達は「今」と「希望」の中に生きていることを教えられた。映画の中の子ども達にもそれと通じるものを感じた。 映画の中で長女が公園の遊具で妹が遊んだ時に残した遊具の上の砂を手で払い、きれいにして帰る場面があった。母親が娘の心に残した数少ない善なる遺産だと思うと胸がいっぱいになった。  無題 2005年6月3日 ショウ 今の当たり前の平凡な生活がどれだけ幸せな事か感じさせてくれた。そして実在の少年、少女たちが当たり前の幸せをつか んでいる事を願う。  ありがとうございます! 2005年6月2日 サリー 是枝監督、すばらしく上質な映画を作ってくれてありがとうございます。 1回目、見終わった後は放心状態のようになってしまって、いろんなことに衝撃をうけてしまいました。 母親が子供を放置して他の男と生活をするとか、子供たちが学校にいってないとか、そういう、リアルなところでの衝撃ではなかった。勿論、そういうベース部分は違うところで受けた衝撃はありましたが。なによりも、子供の視点でした。子供は日常に慣れます。 それが大人の視点からすると、非日常的であったとしても。子供当事者は、日常として受け入れる。受け入れざるおえない。そんな、諦めとか、母へのどうしようもない思慕とか、母へのいらだちとか・・。精神的に奇妙に成長してしまった子供たちの視点が丁寧に慎重に繊細に描かれていました・・・。監督は全て計算して、子供の内面的世界を構築しました。そして、見事に成功しました。 私も子供の頃うけた光とか草花とかにたいする感覚を思い起こさせてくださった監督の力量に驚きと敬意を覚えます。 少し前に中国の「コン・リー」主演の映画「きれいなお母さん」を見ましたが、「誰もしらない」の子供の強さ、「きれいなお母さん」の母親の強さ。子供を愛しているのは一緒だと思う。けど、夫をなくし、一生懸命にすっぴんで子供のために新聞配達をする女、コンリーの姿。子供よりも自分のエゴに生きる女、YOUの姿。そんな対象的な人生も交えながら鑑賞していました・・。 最後に、監督、大好きです!  無題 2005年6月1日 山羊野ひつじ 切なくて切なくて切なくて 私は泣いた。 何でだろう何でだろう何でだろう っておもった。 今までちょっとのことで 「私は不幸だ」 と、思った自分がイヤになった。 自分がわがままに見えた。 私も彼らのように 小さな幸せで喜べる人間になりたい。 この映画を見て、初めて 「世界中の人が幸せになるように」と願った。 
|
||
| previous > |
All rights reserved.